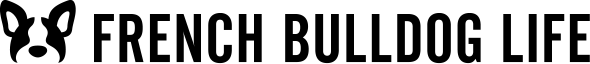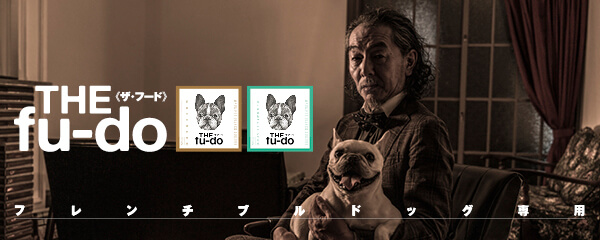フレブルが陥りやすい分離不安について
分離不安っていう言葉、耳にしたことがある人は多いはず。分離不安とはオーナーさんや愛着のある場所から離れると不安や恐怖、ストレスを感じる状態のことで、ずっと吠え続けたり落ち着きがなくなったり、物の破壊や自傷行為などが起きる症状のこと。甘えん坊な犬種はなりやすいとされているけれど、フレブルって甘えん坊ですよね。愛犬の分離不安に頭を抱えている人は決して少なくなく、そして筆者の愛ブヒも少しその傾向があるのです。分離不安症は犬にとっても辛いもの。愛ブヒのためにもこの症状について知り、対策をするに越したことはないんですよ。
筆者のケース

VDB Photos/Shutterstock
思えば先代の愛ブヒも留守番が苦手で、分離不安とまではいかないけれども留守番トレーニングをするのにかなり時間を要しました。
だからこそ2代目ブヒは早くから留守番の練習に取り組もう。
迎える前からそう心に決めていたんです。
が、迎えて数日後にまさかの骨折という怪我をしたため、安静が必要なこともあり目が離せない状況に(今はすっかり回復しています)。
それでなくとも筆者は主に在宅で仕事をしているから、愛ブヒがひとりきりになる機会自体がそもそも少ないんです。

katyapulka/Shutterstock
近所のスーパーに行くぐらいの短時間の留守番は問題ないけれど、これが長時間となると、不安しかありません。
というのも、愛ブヒは先日去勢手術を受けたのですが、病院に預けてからしばらくキュンキュンと鳴き続けていたようで、先生に「分離不安気味です」と言われてしまいました。
とほほ、やはりそうか。
そう思ったのは、迎えてから今まで長いお留守番をさせていなかったから。

BlkG/shutterstock
対処法を聞くと、鳴き続けているときは無視して鳴き止んだら褒めるのを繰り返すこと、短時間の留守番から始め少しずつ時間を伸ばすこと、声かけを行わず外出し、帰宅時も犬が落ち着くのを待ってから相手をすること、というアドバイスをいただきました。
そういえば、先代の時は根気強くこれらを繰り返していたはず。
骨折という予想外の出来事につい甘くなり、いつの間にか留守番トレーニングを怠っていたことに反省することしきり。
懸念材料だった骨折もすっかり良くなったので、これからしっかりトレーニング(これを行動療法と言います)を開始することを誓ったのです。
フレブルは分離不安になりやすい?

Hryshchyshen-Serhii/shutterstock
フレブルでも男の子は特に甘えん坊。
先代や2代目の愛ブヒを見ても、周囲のフレブルオーナーに聞いても、皆口を揃えてそう言います。
分離不安症に陥りやすいのは甘えん坊かつ飼い主への依存度が高い犬種だそうですが、気になって調べるとトイ・プードルやミニチュア・ダックスフンド、ポメラニアン、ラブラドールなどが「なりやすい犬種」にランクイン。
また、迷い犬や保護犬だった経緯を持つ子もなりやすいとされています。

Tienuskin/shutterstock
フレブルの名前は「なりやすい犬種リスト」には入っていなかったどころか、比較的留守番が得意で一人遊びも上手、分離不安にはなりにくい、と紹介している記事も目にしました。
とはいえ、甘えたでオーナーさん命! な性格の子や、飼育環境、飼い主の接し方によって分離不安を発症するのは当然あること。
筆者のケースのようにほとんど留守番経験がなくでひとりになる環境そのものに不慣れであることのほか、例えば今まで上手に留守番ができていた子でも、留守番中に大きな落雷や地震といった怖い経験をしたのが引き金になり発症することも。

Valeriia Khodzhaeva/shutterstock
また、赤ちゃんの誕生や引っ越しなどの変化、オーナーさんとのスキンシップ不足なども要因になるそう。
分離不安の症状も吠える、わざと粗相をするといったものから、ストレスからの嘔吐や下痢、傷になるまで自分の体を舐め続けるといった重度のものまであり、ひどい場合は行動療法と並行し動物病院での薬物療法を勧められる場合もあります。
もしかしてうちの愛ブヒ、分離不安? と思ったら、悪化する前に上記の獣医師のアドバイスにあるトレーニングを始めてみてくださいね。
パピーだけでなく、シニア犬にも起きる

Tienuskin/shutterstock
子犬の時は誰かに面倒を見てもらわなければ生きていけないので、「分離不安」は生存本能として人も犬も生まれ持って備わっていて、大人になるに従いなくなっていくもの。
そう聞くと分離不安はパピー期に多い症状のように思いますよね。
実際筆者の愛ブヒもまだパピー。しかしシニア年齢の犬たちも分離不安を発症しやすいと言われていて、それには目や耳の機能の衰えにより不安や寂しさを感じやすくなることが挙げられています。

Promwat Sintupan/shutterstock
また、甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症、神経疾患や脳疾患などが原因となり発症することもあるため、今まで平気だったのに年齢を重ねてから分離不安が疑われる場合は、動物病院で相談や検査をしてくださいね。
大好きな愛犬といつだって一緒に過ごしたい。
これは多くのドッグオーナーが願うことではあるけれど、現実的には多少なりとも留守番は必須ですよね。
その際に愛ブヒも安心して心地よく、こちらも不安なく外出できるよう、分離不安を克服するトレーニングってとても大事なことなんです。
おわりに

HarryKiiM Stock/shutterstock
自分で書いておきながら、まだ短時間といえども愛ブヒに留守番をさせるのはドキドキする筆者。
ですが、これは愛ブヒのためでもあると言い聞かせ、留守番をさせることを躊躇う己の気持ちに喝を入れています。
人とブヒ、お互いのハッピーなフレブルライフのためには、こうしたトレーニングって欠かせないんですね。
こちらの記事も合わせてチェックしてみてくださいね。
おすすめ記事
-

【取材】ロッチ中岡〜そのフレブル愛、ガチ中のガチ。隠れブヒラバーが語る、細かすぎる魅力とは〜【前編】
みなさんが愛犬家ならぬ“愛ブヒ家”として思い浮かぶ芸能人といえば、草彅剛さん、レディー・ガガさんなど、フレブルを飼っている方が多いと思います。が、ロッチ中岡さんも、じつは大のフレブルラバーだというのをご存知ですか? フレブルを飼っていないのにもかかわらず、中岡さんのインスタグラムを覗くと、たくさんのフレブルアカウントがフォローされていて、わが『FRENCH BULLDOG LIFE』モデルのnicoやトーラスも、その中の一頭。
そんな中岡さんに、フレブルの魅力を語っていただきました。そのブヒ愛っぷりは、思ってた以上! ガチ中のガチでした!?
取材 -

【取材】9歳で脳腫瘍を発症し「4年7ヶ月間」生存。フレンチブルドッグ・桃太郎の奇跡と軌跡
愛犬が「脳腫瘍」と診断されたとき、言葉にできない絶望感を味わうことと思います。筆者も脳腫瘍で愛犬が旅立ったひとり。だからこそ、どれほど厄介で困難な病気かを理解をしているつもりです。「発症から1年生存すれば素晴らしい」とされるこの病気。
ところが、フレンチブルドッグの桃太郎は9歳で脳腫瘍を発症し、なんと4年7ヶ月間も生き抜いたのです。旅立ったときの年齢は13歳と11ヶ月、レジェンド級のレジェンドでした。さらには、治療後3年間は一度も発作が起きなかったといいます。
この事実はフレンチブルドッグだけでなく、脳腫瘍と闘う多くの犬たちに勇気と希望を与えるに違いありません。桃太郎のオーナーである佐藤さんご夫婦に、治療の選択やケアについて詳しくお話しをうかがいました。
取材 -

【取材】上沼恵美子さん「もう一回だけ抱きしめたい」愛犬ベベとの12年間
運命の子はぼくらのもとにやってきて、流れ星のように去ってしまった。
その悲しみを語ることはなかなかむずかしい。
けれども、ぼくらはそのことについて考えたいし、泣き出しそうな飼い主さんを目の前にして、ほんのすこしでも寄り添いたいと思う。
その悲しみをいますぐ解消することはできないが、話をきいて、泣いたり笑ったりするのもいいだろう。
こんな子だった、こんなにいい子だった、ほんとうに愛していたと。
ぼくらは上沼恵美子さんのご自宅へ伺って、お話をきこうと思った。
取材 -
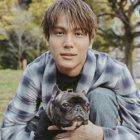
【中川大志インタビュー】エマは犬ではなく、大切な娘です。国宝級イケメンが愛犬のフレンチブルドッグと一緒に登場
『FRENCH BULLDOG LIFE』に国宝級イケメン登場! 俳優の中川大志さんが、愛犬であるフレンチブルドッグのエマちゃん(2歳の女の子)にメロメロとの情報を聞きつけ、中川さんを直撃。そのフレブル愛をたっぷり語っていただきました。他のフレブルオーナーさん同様、濃すぎる親バカエピソードが次から次へと飛び出しました。
取材 -

【取材】川口春奈と愛犬アムのやさしい世界。ー大人気女優は生粋のフレブルラバー
いまをときめく人気女優が、フレンチブルドッグラバーであるという事実。
そうです、その人は川口春奈さん。
アムちゃんというパイドの女の子と暮らしています。
話を聞けば聞くほど、そして春奈さんとアムちゃんのやりとりを目の当たりにするほどに、そのフレンチブルドッグ愛がわたしたちのそれとまったく同じであることに、なんだかうれしくなってしまったのでした。
春奈さんとアムちゃんのすてきな暮らしを、BUHI編集長の小西がいつくしみながら、切り取らせていただきます。
取材 -

【スペシャル対談】愛犬の旅立ちと供養。霊感がない人も「愛犬の成仏」を知る方法!?【シークエンスはやとも×PELI】
愛犬の旅立ちは、誰もが目を背けたくなるもの。けれど事前に知っておくこと、考えておくことで、救われることがたくさんあります。
今回は、お盆スペシャル企画。世間が認めるほどの霊視能力をもつお笑い芸人「シークエンスはやとも」さんに、愛犬の旅立ちや供養についてインタビュー。
インタビュアー兼対談相手は、大の犬好きで心霊分野の知識にも長けているPELIさん。
「愛犬が旅立ったあと、ベッドやおもちゃはどうすればいい?」「お骨はどうするべき?」「お花やお線香は喜んでくれる?」
さらには、霊感がない人でも愛犬が成仏したことを知る方法まで。
お笑い芸人だからこそ暗くなりすぎない、むしろ心がスッと軽くなる。
永久保存版のスペシャル対談です!
対談 -

【取材】千原せいじ「また会う約束を」―動物専門僧侶として伝える、希望の葬儀
お笑いコンビ「千原兄弟」のツッコミを担当する、千原せいじさん。
今年で結成35周年を迎え、芸人としての活躍も目覚ましい中、2024年5月に動物専門僧侶になり世間を驚かせました。
僧侶としての名は「靖賢(せいけん)」。
当時54歳という年齢にして、なぜ動物専門僧侶という道を選んだのか。
また、愛犬の旅立ちとどのように向き合うべきなのか。
「動物専門僧侶」という立場で、お話しをうかがいました。
取材 -

諦めかけた命。あれから2年、フードを変えたら15歳の今もお散歩大好きなフレンチブルドッグに!
今日は15歳の愛ブヒと暮らす、編集メンバーの実体験。
愛ブヒは二年前からすべてのフードが合わなくなり体重が激減。検査をしても異常はなく「年齢のせいですね…」と言われてしまいました。
もう諦めるしかないのかな…そんなとき、我が家に届いたのが「THE fu-do(ザ・フード)」の試食品でした。
そして「THE fu-do(ザ・フード)」を食べつづけて二年、愛ブヒは15歳になり、今も元気にお散歩をしています。
今回は、二年前の絶望から今までを包み隠さず、時系列でお話しさせていただきます。
-

【イベントレポ】5,000頭のフレンチブルドッグと7,000人が集まった「フレブルLIVE2024」の全貌!
11/9(土)-10(日)の二日間にわたって開催された『French Bulldog LIVE 2024(フレブルLIVE)』。
今年はのべ5,000頭のフレンチブルドッグと7,000人のフレブルオーナーが集まりました!
day1の司会はフレブルラバーのロッチさん。day2の音楽フェスには世代ど真ん中のPUFFYが出演するなど、例年以上に豪華なラインナップ。
北は北海道、南は鹿児島県から。全国のフレンチブルドッグが一堂に会した「フレブルLIVE2024」の模様を、詳しくお届けです!
最後には2025年の情報もありますので、要チェックでございます!
フレブルLIVE -
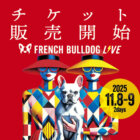
【前売りチケット販売開始!】フレブルLIVE 2025は、11/8(土)9(日)開催!スチャダラパーによるテーマソング制作も決定
『French Bulldog LIVE 2025(フレブルLIVE)』の開催は、11/8(土)-9(日)の2days!
お得な前売りチケット、いよいよ販売スタートです!
さらに今年はビッグニュースが。
なんと、ヒップホップグループ「スチャダラパー」がフレブルLIVEのテーマソングを制作してくれることになりました!
テーマソングの情報やお得な前売りチケットの販売情報など、内容盛りだくさんでお送りしていますので、最後までお見逃しなく!
フレブルLIVE
特集
-

フレンチブルドッグの性格/基本情報
からだの特徴や性格、歴史など基本的なフレブル情報をご紹介!
-

子犬/はじめてのフレンチブルドッグ
フレブルビギナーの不安を解消!迎える前の心得、揃えておきたいアイテム、自宅環境、接し方などをご紹介
-

フレブル病気辞典
獣医師監修のFrenchBulldogLifeオリジナル病気辞典。愛ブヒを守るための情報満載
-

フレブルライフ ストア
本当にいいものだけを、厳選紹介。FBLの公式オンラインストアです
-

French Bulldog LIVE⚡️2025 (フレブルLIVE)
-

【特集】シン・スキンケア
-

【特集】レジェンドブヒの肖像ー10歳を超えて
10歳オーバーの元気なブヒを取材し、長寿の秘訣を探る。
-
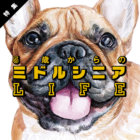
【特集】5歳からのミドルシニアLIFE
ご長寿ブヒをめざすヒントがここに!
-

【特集】編集部厳選!本当に使えるドッグギア
フレブルと暮らす編集部が、自信をもって紹介したいアイテムとは!?
-

【特集】もしものときの名医名鑑
ヘルニアやガンなど、その道の名医たちを独占取材!
-

【特集】永遠の選択。フレンチブルドッグ専用「THE fu-do(ザ・フード)」
-

【特集】わたしは、愛ブヒのリーダーになるのダ。
プロドッグトレーナーが、リーダーになるための秘訣を解説!
-

虹の橋
愛ブヒが虹の橋へ向かう準備をするための場所
-

フレブル里親/保護犬情報
French Bulldog Lifeでは、保護犬を一頭でも多く救うための活動支援をしています。